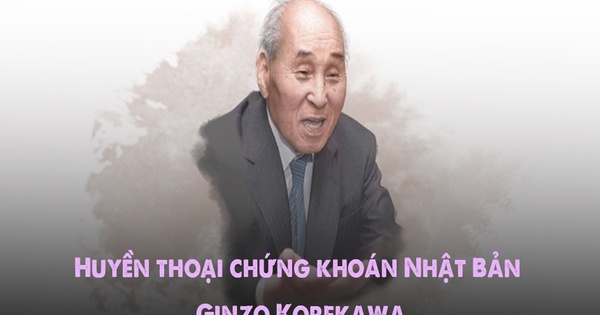毎年2月頃の受験シーズンには、全国のお寺が合格を願う受験生で賑わい、合格祈願の木札を掲げます。 また、縁結びや無病息災、商売繁盛などを祈願する木札としても使われています。 日本人の潜在意識には、願いを込める習慣が深く根付いています。 しかし、絵馬の木札の歴史を知っている人は少ないのではないでしょうか。 この記事でロコビーと一緒に調べてみましょう!
馬はかつて神への供物でした
日本人は馬を神聖な動物と考えています。 この考え方から、昔は馬を寺院に奉納していました。 偉大な寺院にはすべて厩舎があり、神々はこれらの馬に乗って移動したと言われています (今日でも厩舎がいくつかの寺院に残っています)。 生きた馬を繁殖させたり購入したりする余裕のある高位の人々だけがそれらを崇拝することができます。 このため、人々は粘土、木、わらで作られた馬「馬形」を祝うようになりました。 同時に、単純化するために、木の板に馬のイメージを彫ります。 これが絵馬板の原点です。
絵馬木板の最初の記録資料は、平安時代の漢詩集『本朝文随』です。 1012年(刊行9)号に「絵馬三色紙」の記載がある。 また、8世紀頃から木製の絵馬を奉納する風習があったようで、1972年には静岡県浜松市の伊庭で奈良時代(710~794年)の絵馬が出土しました。 2013年、岡山市の鹿田遺跡の発掘調査で、同時代のものとみられる馬の銘板も出土。 伊庭の絵馬は縦約9cm、横約7cm、志方の絵馬は縦約23cm、横約12cm。 現在よく見かける絵馬の原型とも言えます。
室町時代になると、絵馬の質感はより多様化
『ものと人間の文化獅子12絵馬』(岩井宏美・法政大学出版局)によると、絵馬はもともと神社専用のものだったが、室町時代初期には他の塔神社にも広まり始めた。 室町中期に描かれた文様もさまざま。
例えば、滋賀県甲賀県の白山神社に伝わる1436年(永享8年)の絵馬図には、36人の歌人が描かれ、素晴らしい詩が描かれています。 長禄3年(1459年)に制作され、石川県七尾市の王子主主神宮に返還された「女花車有楽絵馬」は、女性の美への願いと、戦乱の平穏を願う気持ちを込めたものです。
戦国時代の絵馬図には、1521年に奈良の興福寺で発見された文殊菩薩像が描かれていました。 弁慶公と牛若丸公を描いた1552年の絵馬も、広島の厳島神社で発見された(主従の誓いと勝利の祈り)。 このように、絵馬図に描かれる絵のバリエーションはますます多様化し、さまざまな歴史的物語を描いていることがわかります。
時代とともに人々の願いは多様化し、絵馬に表現されます。
明治時代、絵馬は通年販売されていました。 絵馬のサイズも多様化。 絵馬灯台は神社に組み込まれており、入り口の上に大きな看板がぶら下がっています。 これをエマカード対応といいます。
特に安土桃山時代(1568~1600年頃)は、きらめく宝石が多かった時期で、高級な大絵馬が多く作られました。 これらのカードは、高位の武士のスケープゴートになりました。
このような絵馬文化は江戸時代に栄え、「絵馬師」と呼ばれる絵師が登場しました。 大衆信仰において欠かすことのできない存在として、彼はますます大衆に知られ、愛されています。 絵馬は初馬を飛ぶように売れさせ、明治時代になってもその人気は衰えることがありませんでした。 変化が起きたのは明治中期。 1892年(明治25年)の読売新聞によると、水天宮の絵馬は1日に300枚売れたそうで、豊穣の神様として知られ、安産祈願の神社として知られています。 通年販売している絵馬もあります。
日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦中、戦争の勝利と幸運を祈る絵馬が作られました。 戦後、縁結びの風習があり、良縁を結び、安泰な生活を送れるよう財運を祈願しました。 年々、初詣時に干支に合わせて絵馬を販売したり、絵馬の色を変えたりするお寺が増え、1960年代には高校・大学受験に第一世代の若者が出場するようになりました。 それ以来、合格祈願のために神社に絵馬を奉納する風習がブームとなり、絵馬は受験シーズンの風物詩となりました。
絵馬に願い事を書いたことのある日本人は少ないのではないでしょうか。 日本人には「困った時は神頼み」という言葉があり、潜在意識に深く根ざした神道信仰を表しています。
紅葉絵馬
この記事があなたが探している情報を提供することを願っています。 詳細を知りたい場合は、この記事の下にコメントしてください。LocoBee の編集者があなたの懸念に対処するための記事を準備できるようにします。
解説に参加するには、LocoBee メンバーにサインアップしてください – 無料です!
ロコビー会員登録
調合:ロコビー

「コーヒーの専門家。謝罪のないツイッターの第一人者。熱心なテレビ学者。インターネットの先駆者。アルコールの擁護者。」